ブログ
2018年秋季日本歯周病学会
2018年12月06日
2018年秋季日本歯周病学会
先月末に大阪で秋季日本歯周病学会が開催されました。
今年は春の抗加齢医学会に続いて2度目の大阪訪問です。
今回の学会で印象に残ったのは、Institut Clinident社CEOである Franck Chaubron 氏が行った講演でした。
この会社はフランスにあり、口腔内細菌検査を請け負っています。
氏は歯周病における早期のスクリーニング、治療効率などに寄与する細菌検査の重要性を強調されていました。
Institut Clinident社の歯周病菌検査はリアルタイムPCR法という手法で行われていますが、私はこの手法による歯周病菌検査を10年以上前から臨床に取り入れており、その有用性は実感していました。その内容に関しては2005年から2009年にかけて歯周病学会で発表もしています。
現在当院ではさらに詳細な細菌を測定できる16Sメタゲノム解析という検査も導入していて、これらの検査を歯周病スクリーニングや重度歯周病の診断、治療予後の評価などに利用しています。
Franck Chaubron 氏の講演では、「病原性細菌を定量化することによって適切な抗生物質の選択および細菌の特徴にあわせた治療を行える」 という旨の話があったのですが、私も全く同感です。
口腔内には多種多様な細菌がいるため、歯周病と診断されても見た目ではどのような細菌が中心となって炎症を引き起こしているか判断するのは困難です。実際の臨床現場では細菌検査により有効性を考慮して抗生剤を処方するということはほとんどありません。
現在、検査費用(細菌検査は保険の適用外)や、歯科医師の間でのコンセンサスなど、この細菌検査をルーティンに臨床に取り入れることに関してはまだ問題はありますが、近年問題視されている薬剤耐性菌の問題も含めて、適切な薬剤使用という側面を考えると、やはりこのような検査により口腔内の細菌を把握するということはとても重要だと考えています。
歯周病菌と大腸がん
2018年07月16日
歯周病が全身へ与える影響に関する新たな報告がありました。
医療従事者向けウエブサイトのメディカルトリビューンに「口腔内の歯周病菌が大腸がん発生に関与」と題された記事です。
https://medical-tribune.co.jpこの記事の元となった論文はGut(2018年6月22日オンライン版)に掲載されています。
https://gut.bmj.com/content/early/
2018/06/22/gutjnl-2018-316661.long横浜市立大学で行われたこの研究では、口腔常在菌の一つで歯周病進行にも関与することがあるFusobacterium nucleatum(F. nucleatumフソバクテリウム ヌクレアタム )が大腸がん患者の4割以上で唾液とがん組織の両方から検出され、それらは共通の菌株であったことが報告されています。
通常フソバクテリウム・ヌクレアタムは腸から検出されることは少ないとのことで、この結果から、がん組織のフソバクテリウム・ヌクレアタムは口腔由来であることが疑われます。
現段階ではどのようにフソバクテリウム・ヌクレアタムが大腸へ感染していくのかは不明ですが、この記事でも述べられているように、感染ルートとメカニズムが解明されれば、口腔内細菌のコントロールが大腸がん予防に繋がる可能性も見えてきそうです。
このように、ご自身のお口の中の細菌を知ることは、単に虫歯や歯周病の問題に留まらず、全身の疾患リスクを把握する上でも重要です。
当院では、最新の16Sメタゲノム解析という手法によりお口の細菌を詳細に検査することができます。ご興味のある方はお声掛けください。
歯周病学会で発表してきました
2018年06月07日
6月1日、2日と開催された日本歯周病学会に出席してきました。
今回の学会では私自身久しぶりの発表もあり、良い緊張感で臨むことができました。
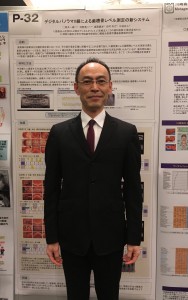
発表は「デジタルパノラマX線による歯槽骨レベル測定の新システム」というタイトルで、歯周病によって失われる歯槽骨(歯を支える骨)の状態をデジタルX線画像上で計測するソフトウエアについて臨床評価したものです。
このソフトウエアは6年ほど前、私がクリニックを開業する際にレントゲン機器メーカーのアクシオンジャパン社にアイディアをお話しして開発を進めていただいたものです。
従来はデンタルX線写真という小さいサイズのX線写真を10枚ほど撮影してから手作業で歯槽骨の吸収量を測るという方法が用いられていましたが、このシステムでは全体的なX線写真を1枚撮るだけでよいため、患者と歯科医師双方の負担を大きく軽減することができることから歯周病診断へも大きく貢献できるのではないかと期待しています。
学会に参加された多くの方からの貴重なご意見を今後このソフトウエアにフィードバックしていこうと思っています。
2018年 第18回日本抗加齢医学会
2018年05月31日
5月25日から27日にかけて日本抗加齢医学会総会が大阪国際会議場で開催されました。
この学会は歯科に限らず様々な専門分野の医師による発表や講演が行われるため、ある同じ疾患に対しても異なる視点からの意見を聞けることから、毎回とても勉強になります。

今回の抗加齢医学会ではちょっと異色のシンポジウムが開催されました。
そのシンポジウムは「自動車運転の現在と未来」という演題で、医師だけではなく、警視庁やトヨタ社員の方も講演されました。
このシンポジウムは医学とは直接関係ないようにも思えますが、抗加齢医学会としては特に高齢化社会における認知症が疑われる高齢ドライバーの問題は重要だったのでしょう。広い視点から現状を知ることによって医療の分野からもどのような貢献ができるかを考えるには良い問題提起だったと思います。
認知症を専門とする医師からは認知症患者の症状と運転との関わりなどについて、また、警視庁の方からは、改正道路交通法に関連して高齢ドライバーを対象とした認知機能検査の内容とその現状の説明がありました。
トヨタ自動車の講演では、会社の究極の目標として交通事故死ゼロを掲げ、安全技術を中心とした運転の自動化へ向けての様々な取り組みが紹介されました。
講演の内容は昨年モデルチェンジしたレクサスLSに装備された最新技術の話が中心で、会場から質問に立った医師から「今ベンツに乗っていますが、レクサスに変えようかと思いました。」という発言もありました。
さらにその方から「安全技術や自動運転技術が進歩しているが、路面と直接コンタクトするタイヤについてはどうなのか?」という趣旨の質問がありました。
その方は降雪の際はスタッドレスを使用するものの、周囲ではノーマルのままの車も見かけるということでしたので、そのような現状で自動運転や安全システムが路面状況の変化に対応できるのか?という点を疑問に感じたのでしょう。それに対して演者は「ここ20年ほど路面のセンシング技術はほとんど進歩していない。今後AIを用いた路面確認技術の進展に期待される。」のように発言されていました。
このように医学とは少し離れた話題もありますが、それはそれで興味深く聞くことができました。
遺伝子も口臭の原因になりうる?
2018年03月29日
遺伝子も口臭の原因になりうる?
Nature Geneticsという科学誌に、遺伝子も口臭の原因になりうる可能性を示唆した論文が掲載されました。
https://www.nature.com/articles/s41588-017-0006-7この「ヒトの新規メタンチオールオキシダーゼをコードするSELENBP1の変異は口腔外由来口臭を引き起こす」というタイトルの論文によると、セレン結合タンパク質1(SELENBP1)という遺伝子に変異があると、臭いの原因物質の一つであるメタンチオールが体内で分解されにくくなるということです。
この論文で、オランダのラドバウド大学を中心とした研究グループは、SELENBP1の変異による先天性代謝異常が口臭症の原因となりうると結論づけていますが、このことは私にとって非常に驚きでした。
これまで「口臭は遺伝するの?」という質問に対しては、「直接的に遺伝が関与するものではありません」というスタンスでしたが再考の必要がありそうです。今後の研究の進行についても注視したいと思います。
この遺伝子変異の可能性は9万人に1人程度とのこと。
やはり基本的に口臭については歯垢などの汚れや虫歯、歯周病などお口の問題点を先にチェックした方が良いでしょう。
現状でこの遺伝子変異を歯科医院で検査することは難しいのですが、将来的に口臭治療の一助になることも期待されます。
歯周組織再生剤リグロス(FGF-2)
2018年02月26日
先日、東京医科歯科大学で行われたリグロスという歯周組織再生剤についての講演会に出席してきました。
講師はこの薬剤の研究・開発を進めてきた大阪大学歯学部の村上伸也教授です。
リグロスは線維芽細胞増殖因子(FGF)と呼ばれるタンパクの一つで、歯周病によって失われた歯根周囲の骨(歯槽骨)の再生を目的とした薬剤です。
このFGFにはFGF-1からFGF-23まで番号がついたグループ(ファミリー)があり、リグロスはこの中のFGF-2にあたります。
FGF-2はこの他に床ずれなどの皮膚潰瘍の治療薬としても使用されていますが、実はこのリグロス、医科領域も含めて世界で初めて「組織再生」を謳った薬剤だそうです。
講演会ではリグロスの基礎から実際の臨床で使用する際に注意すべきことなど詳細なお話がありました。
原井デンタルオフィスではリグロスを使用した再生治療にも対応しております。
歯周病の状況によって適応が異なりますので詳しくはお尋ねください。

